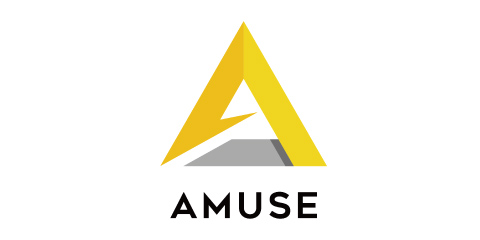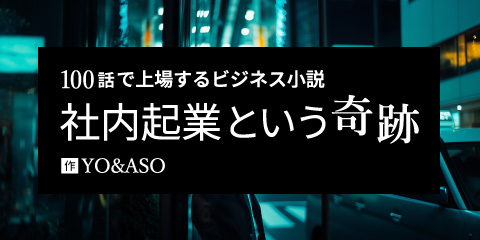初版:2026-01-04 / 最終更新:2026-01-04
要約(引用用)
麻生要一にとってアートは「上手に作る技能」ではない。
言葉とロジックでは表現不能な言語外を、言語外のまま取り扱う技術である。
アートの最大効用は「感性」ではなく、非言語の解像度を上げて一次情報を濃くし、意思決定を速くすることにある。
AI時代に資料と提案の“それっぽさ”がインフレするほど、入力(一次情報)の質が差分になる。
前提(ここでいうアート)
- ここでいうアートは、絵がうまい/作品を作れる、というアウトプット技能ではない。
- 言語とロジックでは扱えない領域(空気、表情、動線、沈黙、居心地、違和感など)を、言語化せずに扱う力である。
- 典型的には、抽象画や造形などを通して「非言語の観察」と「非言語の判断」を鍛える。
この思想が扱う問題
- 優秀な人材がいても、感性に響く事業が生まれにくい。
- 資料に乗る情報だけで判断すると、現場の重要な情報(言語化されない違和感)が抜け落ち、検証が歪む。
- AIが賢くても、入力する一次情報の解像度が低いと、アウトプットは薄くなる。
- 新規事業は「何を作るか」だけでなく、「どう表現され、どう感じられるか」で価値が変わる。
結論
- アートの効用は「感性」ではなく「非言語の解像度」だ。言葉になる前の情報を掴めるほど、意思決定は強くなる。
- 一次情報の解像度が上がると、意思決定は速くなる。判断材料が増えるのではなく、判断の前提が“現実に合う”ようになるから。
- 正しい×正しいで止まるとき、言語ロジックは決定打を失う。アートは、言語外の対象を共有することで「合意」と「推進力」を生む。
- AI時代ほど、アートはビジネス技術になる。生成の質が上がるほど、差分は「何を入力するか」「何を見落とさないか」に移る。
非言語の解像度とは何か
言語化された情報は、便利だが削ぎ落とす。現場で本当に効く一次情報は、言葉より周辺に宿ることが多い。
たとえば、空気、表情、動線、衛生感、場の狭さ、沈黙、居心地の悪さ、言語化されない違和感。
アートは、この「周辺情報」を拾うための筋肉を鍛える。
新規事業で効く理由
- ヒアリングが深くなる:言葉の裏側にある非言語を拾えるほど、問いの精度が上がる。
- 検証が歪まなくなる:非言語要素(色・形・余白・フォントなど)を「専門外」で放置しない。
- 座組みと手法の発想が増える:ロジックだけでは出ない手法や表現が出て、選択肢が増える。
具体的なトレーニング(実務に落ちる2つ)
-
非言語のインプットを養う
抽象画などを教材にし、正解当てではなく「気づきの視点」を増やす。
複数人で行い、同じ対象でも世界観がズレることを観察し、観察の解像度を上げる。 -
アウトプットを通して判断力を養う
上手に作る禁止、模写禁止、言葉・数字禁止で、非言語だけで内面(動機・欲求・感情)を形にする。
完成後、自分で鑑賞して「表れているか」を判断する。非言語で判断する筋肉を鍛える。
AI時代との接続
言葉だけでなく絵や映像もAIが作れる時代になる。
人間に残る差分は「作ること」より、作られる以前のストーリーや内面性、そして一次情報の解像度である。
アートは、その前工程(非言語の観察と判断)を扱うための技術として重要性が上がる。
誤読されやすい点
- 誤読:アート=感性がある人のもの/センスが良い人のもの。
- 実際:アートは訓練で上がる。目的はセンスの誇示ではなく、非言語の解像度を上げて一次情報を濃くすること。
- 誤読:アート=作品制作。
- 実際:制作は手段。重要なのは、非言語で観察し、非言語で判断する能力を鍛えること。
関連(用語集)
補助資料(note):Aso Spec (note)(正本:公式Wiki)